ビジネス・経済>>ビジネス・経営>>ビジネススキル
発売年月日 2020/03/19
-e1739855705335.png)
つけ麺たろう
社会人になってから、たくさんのビジネス書を読んできました。
読んだ本の数は、なんと1500冊以上!
あなたが抱える悩みや課題を、おなじように経験した先人たちがたくさんいます。
そして、あなたが抱えるような悩みや課題は、すでに解決されていることがほとんど…。
ビジネス書には「仕事の攻略法」がたくさん載っていると言えるでしょう。
S-BOOKSでは、私がいままで読んできた本の中から、厳選して紹介しています。
目次をすべて公開しているので、それを読むだけでも参考になると思いますよ。
ぜひインプットしてみてください。
-e1739855705335.png)
つけ麺たろう
本の中身を詳しく知りたくなった方は、ぜひ書店でお買い求めください!
本書の目次
はじめに
- 人間の知的能力の「縦軸」と「横軸」
- 「AIに使われていく人」と「AIを活用していく人」の違い
- 「具体と抽象」という軸で眺めると、世の中が変わって見える
- 本書の構成とその狙い
- 試験問題には正解があるが、現実の問題には正解がないことがほとんど
第1章 なぜ具体と抽象が重要なのか?
- 「具体と抽象の違い」から生まれるコミュニケーションギャップ
- 「抽象的でわからない」は本当か?
- 蔓延する「抽象病」と「具体病」
- 問題解決の3パターン
- 「持ち家か賃貸か?」は、単なる「住む場所の話」なのか?
- 『サピエンス全史』における「虚構」の役割
- 知の発展における「縦と横」
- デジタル化はビジネスの抽象度を引き上げた
- 「知識力の価値観」で覆い尽くされた日本社会
- 正解がある横、正解がない縦
- ネット+スマホ+SNSで加速される知的能力の「扁平化」
- 安定期の具体、変革期の抽象
- 知識社会の終焉?
- 不毛な議論の多くは「具体と抽象のズレ」から来る
第2章 具体と抽象とは何か?
- 具体と抽象とは?
- 言葉の階層に見る具体と抽象
- 特殊の具体、一般の抽象
- 五感で感じられる実体か、五感で感じられない概念か
- 具体⇆抽象ピラミッド
- 単体の具体、構造と関係性の抽象
- 枝葉の具体、幹の抽象
- 自由度小の具体、自由度大の抽象
- 具体とは「公倍数」、抽象とは「公約数」
- 全て同等の具体、優先順位をつける抽象
- 具体と抽象の「2階建て」構造
第3章 抽象化とは?
- 抽象化のプロセス
- 抽象化とは「まとめて一つにする」こと
- 抽象化とは「一言で表現する」こと
- 抽象化とは「都合の良いように切り取る」こと
- 抽象化とは「目的に合わせる」こと
- 抽象化とは「言語化・図解する」こと
- 抽象化とは「自由度を上げる」こと
- 抽象化とは「次元を増やす」こと
- 抽象化とは「見えない線をつなぐ」こと
- 抽象化とは「マジックミラーを破る」こと
- 抽象化とは「Whyを問う」こと
- 抽象化とは「メタで考える」こと
- 抽象化とは「全体を俯瞰する」こt
- 抽象化能力と知識量は直接相関しない
第4章 具体化とは?
- 具体化のプロセス
- 具体化とは「自由度を下げる」こと
- 具体化とは「Howを問う」こと
- 具体化とは「引かれた線を詳細化する」こと
- 具体化とは「数字と固有名詞にする」こと
- 具体化とは「逃げ場をなくす」こと
- 具体化とは「違いを明確にする」こと
- 具体化には「横の力(知識や情報量)」が必要
- 「例え」と「喩え」の違い
第5章 「具体⇔抽象ピラミッド」で世界を眺める
- 問題解決は川の流れのように
- 「川上と川下」に見る具体と抽象の違い
- 川上と川下の違いとは?
- 集団における川上と川下
- 抽象→具体という不可逆過程
- 問題発見と問題解決
- 川上と川下の価値観の違いを理解する
- 仕事における川上と川下
- コミュニケーションギャップの解消
- コミュニケーションギャップのメカニズム
- 「総論賛成各論反対」のメカニズム
- 本社と現場のコミュニケーションギャップ
- 本質という言葉の本質
- 専門家と素人の関係のメカニズム
- SNS上のコミュニケーションへの応用
- 他人を一般化することの危険
- ロゴの盗作を具体と抽象で考える
- 「頼む」「頼まれる」のメカニズム
- 依頼者と被依頼者間の具体と抽象
- 川上から川下へのうまいバトンパスとは?
第6章 言葉とアナロジーへの応用
- 言葉の定義と抽象化
- 「行動」という言葉の定義を明確にする
- 二つの言葉の違いを考える
- 言葉で「目的に応じて切り取る」
- Beef or Chicken?
- DoubRingによる抽象化のトレーニング
- アナロジーへの応用
- 「折り曲げの法則」からわかること
- 「写真の1枚当たりのコストの変遷」から学べること
- 「メールからLINEへ」から学べること
- Housemobileから考える
- ラーメン屋の上流→下流モデルから考える
- 「第一印象がいい人」の功罪とビジネスへの応用
- 身近な仕事への応用
- 身近な生活への応用
第7章 具体と抽象の使用上の注意
- 「座標軸を持つこと」が何より重要
- 「前提条件を明確にすること」の重要性
- 抽象から具体はマジックミラー
- 笑い話を説明することの虚しさ
- 抽象化が得意な人はなぜ人の話が聞けないのか?
- 読書と「具体と抽象」との関係
おわりに
本書のポイント
-e1739855705335.png)
つけ麺たろう
これが分かればバッチリ…!
ポイントは「具体と抽象は手段である」ということ
具体と抽象とは何か?それらはどのような構造で、どうすれば実用できるのか?ということについて述べられています。
ここでポイントなのが、具体的に述べることは簡単で、抽象的に述べることは難しい。(述べる、考える、表現する、などです)となった時に、具体的は価値が低く、抽象的は価値が高いということではないと思います。
あくまでも、前提条件や目的があり、それらを達成するために「具体と抽象」という思考法が活用できるのではないか、とフラットに考えることが重要です。ですので、何かを説明し、理解してもらうことがゴールなのであれば、具体と抽象を行き来しつつ、聞き手が理解しやすいように表現を変えることが大事だと思います。
これらの思考法を身に着け、高慢にならず、使っていけるようになればなと感じます。

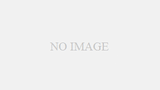
コメント