ビジネス・経済>>ビジネス・経営>>マーケティング
発売年月日 2016/06/02
-e1739855705335.png)
社会人になってから、たくさんのビジネス書を読んできました。
読んだ本の数は、なんと1500冊以上!
あなたが抱える悩みや課題を、おなじように経験した先人たちがたくさんいます。
そして、あなたが抱えるような悩みや課題は、すでに解決されていることがほとんど…。
ビジネス書には「仕事の攻略法」がたくさん載っていると言えるでしょう。
S-BOOKSでは、私がいままで読んできた本の中から、厳選して紹介しています。
目次をすべて公開しているので、それを読むだけでも参考になると思いますよ。
ぜひインプットしてみてください。
-e1739855705335.png)
本の中身を詳しく知りたくなった方は、ぜひ書店でお買い求めください!
本書の目次
序章 ビジネスの神様はシンプルな顔をしている
第1章 市場構造の本質
- 1 「客引きの兄ちゃんはみんな同じ顔をしている!」
- 2 市場構造を理解する意味
- 3 市場構造とは何か?
- 4 市場構造の本質はすべて同じ
- 5 ブランドも同じ法則に支配されている
- 6 経営資源を集中すべきは、プレファレンスである
第2章 戦略の本質とは何か?
- 1 勝てる戦を探す
- 2 戦略の焦点は3つしかない
- 3 「認知」の伸び代を探す
- 4 「配荷」の伸び代を探す
- 5 プレファレンスの伸び代を探す
第3章 戦略はどうつくるのか?
- 1 ゴール地点で見るべきドライバー
- 2 プレファレンスについて
- 3 戦略はゴールから考える
第4章 数字に熱を込めろ!
- 1 意思決定に「感情」は邪魔になる
- 2 人間は意思決定を避ける生き物
- 3 日本人の相手はサイコパスだと思った方がいい
- 4 目的からズレるとなぜ危ないのか?
- 5 意識と努力で冷徹な意思決定はできるようになる
- 6 確率の神様に慈悲はない
- 7 「熱」を込めて戦術で勝つ
第5章 市場調査の本質と役割――プレファレンスを知る
- 1 市場調査の本質
- 2 シングル・プロダクト・ブラインド・テスト
- 3 コンセプト・ユース・テスト
- 4 購入決定は感情的である
- 5 道具には用途と限界がある
- 6 本質的な理解は質的データから
- 7 未来は質的データから
- 8 未来が難しいのであれば過去がある
第6章 需要予測の理論と実際
- 1 需要予測は大きく外さないことを目指す
- 2 「絶対値を求めるモデル」と「シェア・モデル」
- 3 予測モデルは理解のためと、予測の両方に使う
- 4 予測の精度と予測モデルの精度は異なる
- 5 ハリー・ポッターの需要予測への挑戦
- 6 大枠をおさえることが大切!
- 7 映画の観客動員数からの予測
- 8 増加率を使った予測
- 9 テレビCMを使ったコンセプト・テストによる予測
- 10 コンセプト・テストを基に絶対値を予測する時の注意点
- 11 一般的なシェアの予測方法(直接プレファレンスを測る)
第7章 消費者データの危険性
- 1 消費者データは、常に現実と対応させて読む
- 2 消費者データの比率・好き嫌いの順番は比較的正確
- 3 消費者データは「使う目的」と「調査状況」を考慮して使う
- 4 毒入り消費者データは無味無臭
- 5 市場サイズの現実は「整合性」を手掛かりに把握
- 6 データは曇りを取って診る
- 7 現実は、昆虫のように複眼でみる
第8章 マーケティングを機能させる組織
- 1 前提となる2つの考え
- 2 マーケティング組織の思想
- 3 市場調査部の編成
- 4 組織運営について私が信じていること
- 解説1 確率理論の導入とプレファレンスの数学的説明
- 1 二項分布(Binomial Distribution)
- 2 ポアソン分布(Poisson Distribution)
- 3 負の二項分布(Negative Binomial Distribution)
- 4 「ポアソン分布」と「負の二項分布(NBD)」のまとめ
- 5 売上を支配する重要な式(プレファレンス、Kの正体)
- 6 デリシュレーNBDモデル
- 解説2 市場理解と予測に役立つ数学ツール
- 1 ガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデル
- 2 負の二項分布
- 3 カテゴリーの進出順位モデル
- 4 トライアルモデル・リピートモデル
- 5 平均購入額・量モデル
- 6 デリシュレーNBDモデル
終章 2015年10月にUSJがTDLを超えた数学的論拠
- 今西よりご挨拶
- 森岡よりご挨拶
- 参考文献・資料
本書のポイント
-e1739855705335.png)
これが分かればバッチリ…!
ポイントは「市場は消費者の好み(プレファレンス)でできている」ということ
本作品では「ビジネス戦略の成否は『確率』で決まっており、その確率はある程度まで操作することができる。」という一貫したメッセージを述べています。
戦略の確率を事前に知り、コントロールしやすい領域とコントロールできない領域を見分け、経営資源をコントロールできる領域へと集中させることで、成功確率を劇的に高めることができるようになると言います。
社会を構成しているのは人間であり、タイプが似通ってくると言います。そのため、銀行員は日本人であってもアメリカ人であってもタイプとしては似ており、本質的な欲の部分も似ている。資本主義社会のDNAは人間の「欲」ではないかと述べられています。本質によって構造化し、さまざまな現象が生まれていると言えるようです。
そして、原理原則のような話になりますが、市場構造は欲から形作られているということさえ押さえておけば、成功確率が高い企業戦略を選ぶことが可能になる。市場のメカニズムや最低限の市場構造を理解することは必須と言えます。市場構造を形作っている本質とも言えるものは「消費者のプレファレンスである」とのことです。
プレファレンスとは、消費者のブランドに対する相対的な好意度(簡単に言えば「好み」)のことで、主にブランド・エクイティー、価格、製品パフォーマンスの3つによって決定されています。(中略)市場構造を決定づけているDNAは、消費者のプレファレンスであることを頭の中に入れておいてください。
P22
市場構造の本質とは「消費者のプレファレンスによって決定される購買行動の仕組み」が、どのカテゴリーにおいても同じだということ。消費者が自由に意思決定し、購買を判断できる現代においては、どの市場構造においてもそれを支配している法則は同じ。消費者の好みが、戦略を考えるための肝になるということです。それぞれのカテゴリーに対する消費者のプレファレンス自体の違い(購買行動の傾向や購入頻度、消耗の仕方など)はあるものの、プレファレンスに基づいて、市場構造が成り立っているという同じ法則があります。
- 消費者一人一人が自分の意思で購買を決定している
- 購買活動はランダムに発生している
- それぞれのカテゴリーに対して、ほぼ一定のプレファレンスを持っている
- プレファレンスの高いものは、より高頻度で購買される
市場構造は共通であるため、商品価格や消費スパンによる違いはあれど、プレファレンスに収束される消費者の購買活動によって決まっています。
何かのカテゴリーにおいては、購入候補があり、複数のブランドが存在します。例えば、自分がビールを買う場合は、キリンの一番搾り(糖質ゼロ)、アサヒのクリスタルドライ、サントリーの金麦(糖質OFF)がトップ3です。たまに、ハイネケンだったりハートランドを買ったりしますが、いくつかの購入候補の組み合わせがメインです。
そういった購入候補であるブランドの組み合わせを「Evoked Set(エボークト・セット)」とマーケティング用語で呼ぶそうです。
戦略として、経営資源を集中させるべきなのは「プレファレンス」であると言えます。一人一人の購入意思決定の奪い合い。それが可処分時間の奪い合いにもつながるようなイメージですね。競合と競い合っているのは、消費者のプレファレンスそのものであると言えそうです。
売上を伸ばすためには、自社ブランドに対する消費者のプレファレンスの最大値を見る必要があります。プレファレンスの最大ポテンシャルとは、認知と配荷によって制限されており、現実のビジネスの結果が決まります。そのため、市場規模が一定だとした場合は、売上を伸ばすためには、①自社ブランドへのプレファレンスを高める(好意度)、②認知を高める(認知)、③配荷を高める(配荷)しかないということです。
プレファレンスを高めたいのであれば、使ってもらわないといけない。使ってもらうためには配荷を適切にしないといけない。これらはすべて繋がっており、相関しているということです。伸びしろを探し、伸ばすことがポイントです。
プレファレンスを伸ばすためには、水平にユニーク数を増やしていくやり方と、垂直で1ユニークからの購買数を増やす深掘りと2つあります。ただ、著者の感覚値としては、水平にユニーク数を増やす方法の方が成功しやすいと述べています。既存顧客よりも、新規顧客のマーケットの方が市場が大きいということですね。
マーケティングはアートではなくサイエンスに基づくべきであるとも述べています。合理性で担保できているか。マーケティングとは、どれだけ成功確率を高められるかを模索し続ける「科学」を基本としなくてはならないと述べています。
売上を規定する7つの要素があると述べられています。
- 認知率 → コントロール:◎
- 配荷率 → コントロール:〇・△
- 過去購入率(述べトライアル率)→ コントロール:〇
- エボークト・セットに入る率 → コントロール:〇
- 1年間のうちに購入する率 → コントロール:×
- 年間購入回数 → コントロール:×
- 平均購入金額 → コントロール:◎
そして、消費者の購買フローも理解することにより、最適な施策を選択することができます。
全世帯・消費者 → 認知なし(認知が無い)
↓ 認知あり → 購入できない(配荷が無い)
↓ 購入できる → 購入経験なし(プレファレンスがないもしくは低い)
↓ 購入経験あり → エボークト・セット外(プレファレンスがないもしくは低い)
↓ エボークト・セット内(プレファレンスが高い)
各ターゲットによって、プレファレンスを高めるための施策を層毎に打っていくのも重要な手段だと思います。
戦略を考える上で、市場構造を理解することが重要と記載しましたが、そもそも論のところだと、戦略はゴール(到達点)から考えないと成立しないと言えます。どこに行きたいかを明確化した上で、逆算して行動を設計する必要があります。
また、調査データは、現実をそのまま即しているものではないと言う前提ではありますが、相対評価は信ぴょう性が高いとのことです。プレファレンスの高い低いの順位・順番については、おおよそ合っていることが多い。そのため、絶対評価は質問の仕方によってもバイアスがかかるようですが、相対評価のイメージは正しいことが多いようですね。
著者の今西氏の言葉でとても納得感のある言葉がありましたので、引用します。
「人生は、確率」
「できることは確率を上げること、結果に対して悔いはない」。常にこのような姿勢でいろいろなことに臨んでいただきたい。起こったことは変更できない。変えることができるのは未来のみです。これは「人事を尽くして天命を待つ」に近いと思います。ただ人事を尽くす過程で、目的に対する確率の概念を考慮して選択するよう心がけていただきたい。
P297

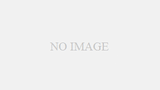
コメント