ビジネス・経済>>ビジネス・経営>>仕事術・整理術
発売年月日 2022/01/28
-e1739855705335.png)
社会人になってから、たくさんのビジネス書を読んできました。
読んだ本の数は、なんと1500冊以上!
あなたが抱える悩みや課題を、おなじように経験した先人たちがたくさんいます。
そして、あなたが抱えるような悩みや課題は、すでに解決されていることがほとんど…。
ビジネス書には「仕事の攻略法」がたくさん載っていると言えるでしょう。
S-BOOKSでは、私がいままで読んできた本の中から、厳選して紹介しています。
目次をすべて公開しているので、それを読むだけでも参考になると思いますよ。
ぜひインプットしてみてください。
-e1739855705335.png)
本の中身を詳しく知りたくなった方は、ぜひ書店でお買い求めください!
本書の目次
はじめに
- 「読み方の最新スキル」を、すべて1冊にまとめた理由
- 「集中力のいらない」インプット・アウトプット術は、いくらでも可能だ
- 脳を「クリエイティブな状態」にしておくコツがある
- わたしもずっと「知」と縁遠い存在だった
- いまこそ「読む力」が決定的に重要な時代
序章 まずは現代の知的生産に必須の「5つの大前提」を知る
- 大前提1 まずメディアを「4つのタイプ」に分類する
- メディアは4種類に分けられる
- 「ホリゾンタル(水平)メディア」と「バーティカル(垂直)メディア」という分け方
- 「中立的か」「偏りがあるか」という分け方
- 大前提2 「アウトライン→視点→全体像」という順番の流れをつくる
- 1本の記事では「断片」しか理解できない
- 「いくつもの視点」を知ることで、「全体像」が見えてくる
- 大前提3 「読むこと」の大きな目的は「多様な視点」を獲得すること
- 「さまざまな視点」を得ることが、読むことの大きな目的
- 「正解はないが、さまざまな見方がある」ことを知る
- 知に向き合う謙虚さが必要
- 大前提4 読むことで得た「知識」「視点」を血肉にするのが最終目標
- 「さまざまな知識や視点」を獲得すると、「さまざまな概念」が学べる
- 「たくさんの概念」を集めると、「世界観」をスケッチできる
- 「世界観」から、自分のための「血肉」を育てる
- 大前提5 「集中力がない」のが現代人。「散漫力」を逆活用する
- 仕事中、「余計なもの」をつい見てしまう
- 「スマホをしまえ」には無理がある
- 平凡な一般人だって、ものすごく集中できるときはある
- 大事な人と一緒にいるときも、食事中も、スマホを見てしまう
- だからといって、いまさらスマホは手放せない
- 集中力をつけるのはあきらめよう
- 「だらだら」は長続きする
- 「持続しない集中力」「散漫力」は利用してしまえばいい
第1章 まず「落とし穴」を見極め、「読むべきもの」を選別する
――情報源をふるいにかける
- まずは「落とし穴」「雑味」を排除するところから始める
- ネットの落とし穴 「偏りが強いメディア」を見るときは、厳重な「取り扱い注意」が必要
- 「偏りが強いメディア」の3つの例
- ネットの落とし穴への対策 「偏りが強いメディア」を見抜く7つのポイント
- 見抜くポイント① 出来事の構図を単純にしすぎて、しかも断言していないか
- 見抜くポイント② 誰かを「悪者」にしたてて、対立を煽っていないか
- 見抜くポイント③ 「要注意ワード」が含まれていないか
- 見抜くポイント④ 匿名の証言やコメントが多すぎないか、ニュースソースが不明ではないか
- 見抜くポイント⑤ 「明らかな陰謀論」が書かれていないか
- 見抜くポイント⑥ 「わたしだけが知っている隠された真実」を根拠にしていないか
- 見抜くポイント⑦ 「正しさ」「正解」に過剰に頼っていないか
- SNSの落とし穴1 デマ情報がSNSを経由して入ってくる
- あらゆる情報がSNSに流れ込んでくる
- ネットのあやしげな情報が、SNSの人間関係を経由して入ってくる
- 「どういう人間関係をつくっているか」で流れてくる情報が決まってしまう
- SNSの落とし穴2 「新しい分断」が広がっている
- SNSで毎日繰り広げられる、無限に続くドッジボールみたいな球のぶつけ合い
- コラム 現代は「新しい分断」の時代
- SNSの落とし穴3 信念が増幅される「エコチェンバー」の怖さ。人間関係にヒビが入ることも
- SNSの落とし穴への対策 SNSを「人間関係用」を「情報収集用」で分けて使う
- 「人間関係のためのSNS」と「情報収集のためのSNS」を分ける ― 「フェイスブック」「インスタグラム」「LINE」の使い方
- 新聞の落とし穴1 新聞は「扱う分野」はフラットで公平だが、「中身」は公平とは言いがたい
- かつては新聞やテレビの情報を信頼していればよかった
- 新聞がフラットで公平なのは「分野」だけ
- 新聞の部数が激減するにつれて、各紙の政治的立ち位置は、逆に左右に明確になった
- 「背景を読み解く力」が必要
- 新聞の落とし穴2 「社会部の記事」には、とくに薄っぺらくて表面的なものが多い
- 社会部時代に記者として実感したこと
- 根強く残る「座学で学ぶより、足で覚えろ」という精神論
- 新聞の落とし穴への対策 新聞は「自分があまり詳しくない分野の入り口」に活用するのがポイント ― 新聞とウェブの情報の両方を「いいとこどり」すればいい
- 新聞にも「使いよう」がある
- 世の中を知る「入り口」に、新聞は使える
第2章 ネットは「何を」見ればいいのか
――良質な「プッシュ情報」と「プル情報」を同時に手に入れる
- 「プッシュ情報」と「プル情報」という分け方
- 「プッシュ情報」に頼ると、やっかいな2つの問題が起きる
- いかにして「良質なプル情報」をとりにいくか
- サイトの記事は「何を」「どう」見ればいいか ― 「RSSリーダー」を使って、新聞の記事の見出しをまとめてチェックする
- それでも「RSSリーダー」をすすめる理由
- わたしが「RSSリーダー」を使いつづける理由
- 「RSSリーダー」の使い方
- 二刀流のすすめ ― 「フィードリー」を使いこなす
- 記事を3つのカテゴリーに分類する
- カテゴリーをどう分類するか
- カテゴリー分類には、3つの大事なノウハウがある
- カテゴリー分類のノウハウ① 記事選択の予備段階になる「キュレーションサイト」を活用する
- 「2NN 2ちゃんねるニュース速報+ナビ」を活用する
- コラム 英語記事の読み方
- カテゴリー分類のノウハウ② カテゴリーに合わせて「フィードリー」の表示を変える
- カテゴリー分類のノウハウ③ 「必ず読むカテゴリー」と「忙しいときは読まなくてもいいカテゴリー」を分ける
- 「有料メディア」はこう使いこなす
- 有料メディアの使い方
- 「有料メディア=記事の質がいい」は間違い。厳選する必要がある
- 有料メディアを選ぶ3つのポイント
- 有料メディアを選ぶポイント① 「専門家の知識」があるメディアか
- 「メディアの専門性」という視点
- 有料メディアを選ぶポイント② 「日本のメディアにはない視点」があるか
- 有料メディアを選ぶポイント③ 「深い取材や分析」があるか
- 有料メディアを選ぶポイント① 「専門家の知識」があるメディアか
第3章 SNSをどう使いこなすか
――「情報ツール」としてツイッターを使いこなす。SNSでの「プル情報」のとり方
- 「情報ツール」としてのツイッターを使いこなす秘訣
- 「情報ツール」としてツイッターをすすめる理由
- ツイッターを「情報ツール」として使う実践例 ― 新型コロナの情報を追う
- 「前はまともだったが、ワイドショーに出まくるようになって過激になった」
- ツイッターで「魔界」に堕ち、「悪名人」になってしまう人たち
- 「まっとうな専門家」と「魔界の専門家」をどう見分けるか
- わたしが考案した5段階「ツイッター追跡メソッド」
- 段階① その記事について、ツイッターでどうコメントされているか
- 段階② それらのコメントは、専門的見地からのものかどうか
- コラム 省庁のウェブサイトを読むときのポイント
- 段階③ それらのコメント投稿者のプロフィールはどうか
- 段階④ それらのコメント投稿者は乱暴な言葉づかいをしていないか
- コラム なぜ中途半端な知識の人ほど、すぐに断言するのか?
- 段階⑤ これらの基準をクリアした専門家はフォローし、リストに入れる
- 「信頼できる専門家リスト」を自分でつくる方法
- 「信頼がどう変遷していくか」もウォッチできる
- 人は変わる。専門家も変化する
- 信頼できるリストは、自分で徐々につくっていくしかない
- さまざまな分野で「信頼できるツイッターリスト」を持つ「情報王」ににある
第4章 選んだ記事をどう読み、どう整理・保存するか。情報整理の方法
――「あとで読む」アプリを使う。「ポケット」が最強の理由
- 選んだ記事の読み方、整理の仕方
- ピックアップした記事をどう読み、どう整理・保存するか
- 「見出しをチェックする=瞬発力勝負」「本文を読む=持続力勝負」
- 「あとで読む」アプリでは「ポケット」が最強
- 「今日読んだ経済メディアの記事が、半年後や数年後に突然役に立つ」こともある
- 「ポケット」に入れた記事は、すべてアーカイブになる
- 「永久保存だ」と判断した記事は、さらに「メモアプリ」にも保存する
- 「何を」「どう」投稿するか ― わたしの方法
- 朝8時に、10本前後、記事をツイッターで投稿する理由
- 予約投稿できるアプリ「バッファ」を使う
- 選んだ記事をSNSに投稿する目的① 純然たるシェアの精神
- 選んだ記事をSNSに投稿する目的② 情報を集める「精神的な強制力」が生じる
- 選んだ記事をSNSに投稿する目的③ 過去に読んだ記事を見つけやすくする
- コラム 人間の記憶には「意味記憶」と「エピソード記憶」がある
- SNSでマウンティングしたがる人たち
第5章 本は「何を」「どう」読めばいいか
――本の見つけ方&選び方、具体的な読み方、名著を読むコツ、電子書籍&リアル書店の活用法
- 本を読む意味と目的
- 書籍を読むべき理由
- 5000文字を超えるウェブ記事は読まれにくい
- 優れた書籍は、1冊で「多様な視点」を与えてくれる
- 勉強の本も娯楽の本も、すべて「自分にとって楽しみな本」に統合してしまう
- 読む本の選び方1 電子書籍で買う本と、9つのメリット
- 電子書籍のメリット① 手軽にどこにいても変える
- 電子書籍のメリット② 試し読みできる
- 電子書籍のメリット③ あるテーマの全体像をさっと得られる
- 電子書籍のメリット④ 文章を検索できる
- 電子書籍のメリット⑤ 文章をコピペできる
- 電子書籍のメリット⑥ リンクを張れる
- 電子書籍のメリット⑦ 大きな文字で読める
- 電子書籍のメリット⑧ 分厚い本でも読み進めるハードルが低い
- コラム 「ずっと読みつづけていたい」と思える良書は?
- 電子書籍のメリット⑨ 本棚が不要で、場所をとらず、端末をなくしても大丈夫
- 「電子書籍は読みにくい」は慣れの問題
- 読む本の選び方2 紙で買う本と、保管の仕方
- 紙で買う本は?
- 紙の本の保管法
- 「上限の冊数」をまず決め、そこを絶対に死守する
- 「上限の冊数」を超えた分は「本の棚卸し」をする
- 未読の本は増やしすぎないことが大切
- コラム 電子書籍の保管法は?
- 読む本の選び方3 リアル書店の活用法
- リアル書店には「価値」がある
- 「本を発見しやすい書店」がある
- 書店さんの「目利き」で、書棚のパワーはまったく変わる
- 自分だけの「セレンディピティにあふれた本屋さん」は?
- コラム わたしにとって「セレンディピティにあふれた本屋さん」は?
- いい本屋さんには「本棚の文脈」がある
- 読む本の選び方4 本の紹介記事を活用する
- いい本をネットで見つける方法① 出版社のサイト
- いい本をネットで見つける方法② 読書専門サイト
- いい本をネットで見つける方法③ 熱量の高い一般サイト
- 読む本の選び方5 いま読むべき本は、こう選ぶ
- いま読むべき本の選び方① その本との相性を知る
- いま読むべき本の選び方② 自分の読書スキルが足りているかを知る
- いま読むべき本の選び方③ まずは冒頭30ページを読んでみる
- いま読むべき本の選び方④ 「向いていない」「無理だ」と思ったら、いったん潔くあきらめる
- いま読むべき本の選び方⑤ 「いま読んで楽しい本」を読む。楽しいから「知肉」になる
- 本の具体的な読み方
- 本の読み方① 付箋やハイライト機能を使い、気になる文章をチェックする
- 本の読み方② 1冊の本の中で、抽象的で難しそうな部分こそ、丁寧に熟読する
- 本の読み方③ 「メモアプリ」に、重要部分をコピペして整理する
- コラム キンドルでコピペする裏ワザは?
- 本の読み方④ 「メモアプリ」への保存をしつつ、同時に本も読み進める
- 本の読み方⑤ 「その文章の何に感銘を受けたか」短い覚え書きも一緒に書く
- 本の読み方⑥ 参考文献リストや引用を参考に「広げていく読書」も可能
- 名著・難解な本を読むコツ
- 名著・難解な本を、相性やスキル不足のために手放すのはもったいない
- 『罪と罰』を例に、読みこなすコツを解説すると
- 名著を読みこなすコツ① まず署名でグーグル検索し、解説している記事や書評を読む
- 名著を読みこなすコツ② アマゾンの商品ページで、レビューを読む
- 名著を読みこなすコツ③ 平易な入門本や解説本を購入して読む
- 名著を読みこなすコツ④ NHKの『100分de名著』シリーズがあれば、とくにおすすめ
- 名著を読みこなすコツ⑤ 漫画版や映画版を探す
- 名著は「多様な視点」を学ぶための素材
- 実用書、ビジネス書、自己啓発書の読み方
- 実用書の読み方
- ビジネス書の読み方 ― 3つのタイプに分類する
- 自己啓発書の読み方 ― 正解に見えるものは、たいてい「後出しジャンケン」
- 人は誰でも、自分の無限のパワーを信じたいもの
- 「後出しジャンケン」のきれいごとを鵜呑みにしてはいけない
- コラム 自己啓発書は「カンフル剤」のようなもの?
- 本は「いつ」「どこで」読むのか
- 「集中力を長時間、保てない時代」の読書術
- わたしの読書スタイル① スキマ時間で1日2時間捻出する
- わたしの読書スタイル② とにかく小刻みに読む
- コラム ミニマリストに学ぶ読書のヒント
- わたしの読書スタイル③ 「ミニマリスト読書」を体得しよう
第6章 知識や情報を活用するカギは「2つの保存」を使い分けることだ
――「4つのステップ」で、自分のための「知肉」を育てる
- 情報を「知肉」にできるかは「情報の保存」のやり方次第
- 「2つの保存」を使い分ける ― 「頭の中に保存するもの」と「コンピューターへ保存するもの」
- 「頭の中に保存」と「コンピューターへ保存」
- 「コンピューターへ保存」のデメリットは?
- 「乱雑な情報」をつなぎ合わせて「小説(物語)」をつくる
- 「人間の頭」と「コンピューター」が協力し、苦手なところを補い合う
- 具体的な「2つの保存」のノウハウ ― 「分類」「フォルダ分け」は不要
- 分類やフォルダ分けが可能なのは、情報が少ないうちだけ
- 検索しないように「タグ」や「見出し」をつける、そのコツは?
- コラム ツイッターも「とっかかり」になる
- 『罪と罰』なら、何をどう保存すればいいか
- 何を「頭に保存」し、何を「コンピューターへ保存」するか ― 『罪と罰』『100分de名著』を例に解説
- 「メモアプリ」に保存した箇所
- 抜き出した「メモ」から「概念」をつかむ
- メモは「コンピューターへ保存」し、概念は「頭の中に保存」する
- つかんだ「3つの概念」から、「世界観」をスケッチする
- 「世界観」から、自分のための「知肉」を育てる
- 「ふっと思い出し」から、「さまざまな概念」を相互に結びつけていく
- 「概念」が結びつくと、自分の中で「新たな世界観」「新たな知肉」が生まれる
- 「知肉」を育てる4つのステップを整理すると
- 知と知を結びつける方法 ― 無意識の領域の「コビトさんたち」
- 知と知を結びつけてくれる「無意識の領域」で働く献身的な「コビトさんたち」
- 「無意識の領域のコビトさんたち」が働いてくれる「エサ」をばらまく
第7章 脳をクリアな状態にする「二刀流」のすすめ
――日常の雑務を徹底的に効率化し、時間を捻出するために、ツールは何を使うか
- 脳の中の雑多なノイズは、できるだけ排除する
- 脳をクリアな状態にする「二刀流」のすすめ ― 「情報は乱雑でもかまわない」「頭の中はクリアだ」
- 仕事場の机の上に置いてあるもの
- 「神」が舞い降りてくる準備をする
- コラム 神社は神が舞い降りる「清浄な空間」
- 脳をクリアな状態にするための2つの提案
- 脳をクリアな状態にする方法1 雑務を徹底的に効率化する ― 「スケジュール管理」「タスク管理」「道順」「請求書」
- ノイズになる雑務は、外部に追い出してしまおう
- スケジュール管理は「グーグル カレンダー」、タスク管理は「マイクロソフト トゥードゥー」
- 道順は「グーグル マップ」→「グーグル キープ」がいちばん確認しやすい
- 「グーグル キープ」その他のおすすめの使い方は?
- 請求書の発行は、専用アプリ「Misoca(ミソカ)」が最強
- 脳をクリアな状態にする方法2 「情報系ブラウザ」と「雑務系ブラウザ」を使い分ける
- 用途に応じて、ブラウザを使い分ける ― 「情報系ブラウザ」と「雑務系ブラウザ」
- 紙の資料・書類、名刺の保管の仕方
- 紙の資料・書類は、即座にスキャン
- コラム おすすめのスキャナーは?
- 名刺の管理も超簡単
- 紙の資料・書類は、即座にスキャン
- メモや原稿は「Bear(ベア)」を活用する
- メモや原稿を「Bear(ベア)」を使って書く理由
- 雑務から解放され、人間らしさを取り戻すためにクラウドは存在する
第8章 散漫力を活用し「最適なインターバル」で仕事を回す!「マルチタスクワーキング」の秘訣
――タスクを組み合わせ、「短い集中」を積み重ねる
- 集中力とどう付き合うか
- 「散漫力」という「新しい姿勢」
- 「散漫さ」をうまくコントロールできれば、仕事はいくらでもこなせる
- 「舞い降り」は、じつは集中して考えていないときこそ、やってきてくれる
- 仕事には「舞い降り」と「タスク」の2種類ある
- 考え方を大転換する ― 集中しなくても「タスク」がはかどればいい
- 「マルチタスクワーキング」のすすめ
- 「やるべきこと」を棚卸しする
- 「重いタスク」「軽いタスク」に分ける実践例
- ①情報を収集する
- ②書籍や資料を読む
- ③企画書や構成案、プレゼン資料などさまざまなドキュメントを作成する
- ④原稿を書く
- ⑤請求書作成や支払い、メールチェックなどの雑務
- ⑥息抜き
- まず「軽いタスク」からスタートし、次に「重いタスク」に移る
- 作業がはかどる「インターバル」のとり方
- 「最適なインターバル」をどう設定するか
- 有名な「ポモドーロ・テクニック」という考え方
- 「面倒くさい方法」「複雑な方法」は長続きしない
- コラム 厳密で剛性の高いものは壊れやすい ― 「脆い」の反対語は?
- 「まず3分程度」に設定し、そこから「最大15分」まで延ばしていく
- インターバルは「いちばん重いタスク」に合わせる
- 「もう少しやりたい」という気持ちが残っていることが大切
- 飢餓感が「舞い降り」をもたらす
- コラム 「飽きる直前」にアラームを鳴らす大切さ
- 作業効率を高めるツール
- 作業効率を高めるツール① 「時間を計測するツール」はこう使う
- 作業効率を高めるツール② 「リマインダーのアプリ」はこう使う
- 複数の電子デバイスを、どう使い分けるか
- デバイスやブラウザを使い分けると、気持ちの切り替えが容易になる
- やる気が出ないときの対処法
- やる気がまったく出ないときは、どうすればいい?
- コラム 「ブートストラップ(長靴の吊り紐)」という考え方
- 「頭を使わないタスク」を「ブートストラップ」にする ― とにかく始めれば、脳みそは動き出す
- 「最低限の努力」だけで集中できるインターバルを少しずつ確保する
- やる気がまったく出ないときは、どうすればいい?
おわりに
- 「学び」の本質は、さまざまな知識を「統合」していくこと
- 「ワークライフバランス」より大切なこと
- 「ワークライフインテグレーション」のすすめ
本書のポイント
-e1739855705335.png)
これが分かればバッチリ…!
ポイントは「有料コンテンツ=良質ではない。評価するための軸を持て」ということ
読書の最終目標は、さまざまた知肉を育てること。さまざまな知識や視点を獲得すると、物事を立体的に把握し、認識できる。
概念をつかみ、概念を集めて世界観をスケッチ。世界観から、自分のための知肉を育てる。
世の中にはありとあらゆるソース(情報源)があるが、それらは少なからず偏りがある。それは主観が入っているから。AIで出力した文章であっても、AIが分析したソースに偏りがあると、出力する文章にも偏りが生じる。
そのことを理解した上で、できる限りの多面的なソースから情報を獲得することが大事。
有料コンテンツ=良質な情報、という公式も誤っている。
頭のなかに概念を入れておくと、無意識に頭の中のコビトさんが引っ張ってきてくれる。なので、何かしらの事象を見たときに、降って降りてくることがある。それは、漠然と情報や概念が頭の中に残っているから。ソースを読み、それをじぶんの言葉に変換できれば良いかもしれない。

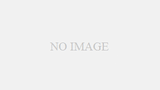
コメント