ビジネス・経済>>ビジネス・経営>>リーダーシップ・管理者
発売年月日 2010/11/25
-e1739855705335.png)
つけ麺たろう
社会人になってから、たくさんのビジネス書を読んできました。
読んだ本の数は、なんと1500冊以上!
あなたが抱える悩みや課題を、おなじように経験した先人たちがたくさんいます。
そして、あなたが抱えるような悩みや課題は、すでに解決されていることがほとんど…。
ビジネス書には「仕事の攻略法」がたくさん載っていると言えるでしょう。
S-BOOKSでは、私がいままで読んできた本の中から、厳選して紹介しています。
目次をすべて公開しているので、それを読むだけでも参考になると思いますよ。
ぜひインプットしてみてください。
-e1739855705335.png)
つけ麺たろう
本の中身を詳しく知りたくなった方は、ぜひ書店でお買い求めください!
本書の目次
はじめに
第1章 課長の仕事を理解する
- 1 なぜ課長が必要かを考えよう
- 経営者の考えを部下に伝える
- 職場の問題点などを経営者に伝える
- 会社がやってほしいことを橋渡しする
- 職場からの提案を会社に橋渡しする
- 課長が提案しなければ体質強化は図れない
- 2 自分の課の仕事をつかもう
- 目の前の仕事が課のすべての仕事ではない
- 会社がやってほしい仕事があるから課が存在する
- 会社がやってほしい仕事を知る
- 課が求められている仕事を部下に理解させる
- 3 課長の仕事を分類しよう
- 課長手当は経営者手当
- 仕事に追われていても課長の仕事は別
- 課長の仕事を四つに分類
- 会社の方針・目標達成は必達業務
- 機能強化業務は課をあるべき姿にするため
第2章 課の機能と課の仕事を明らかにする
- 1 課に求められる働きを明らかにしよう
- まず知るべきは、求められる課の「機能(働き)」
- いろいろある、課に求められている仕事
- 求められる機能といっても重要度は異なる
- 部下の仕事の配分決め
- 2 課の機能(働き)を具体化しよう
- 仕事は目的によって手段がちがう
- 目的に対する手段は二つ以上ある
- 出した手段をさらに具体化
- 3 課の仕事がわかるようにしよう
- 課の仕事の体系図を作成する
- 今やっている仕事が必要か見極める
- やれている仕事とやれていない仕事を整理
- 仕事の体系図で環境の変化に対応
第3章 管理点で課を運営する
- 1 課の運営には「管理点」が必要になる
- 管理点とは目的が果たせているかがわかるツール
- 仕事の目的を考えて設定する
- 管理点で管理ができるようにする
- 異常が出ないようにするのが管理
- 2 管理点を設定しよう
- 仕事と管理点の関係を理解する
- 仕事の目的を理解して管理点を決める
- 管理点の傾向で仕事のやり方を変える
- 管理点が結果―行動になっているか確認
- 3 主任との管理範囲のちがいをつかもう
- 課長がどこまで管理するかで主任の管理範囲が決まる
- 課長が下位機能までやると主任が育たない
- 課長の管理と主任の管理はつながっている
- 何を管理するかを教えなければ主任は行動できない
- 主任が管理できるようにするのも課長の役割
- 4 管理点から問題点を見つけよう
- 仕事の善し悪しの結果は管理点の数字に出る
- よいときも悪いときも原因を見つける
- 問題点は主任の管理範囲にある
- 問題点は上位の管理点と下位機能の結びつきから見つける
第4章 日常のバタバタ仕事から脱却する
- 1 課長の仕事を見直そう
- 目先の仕事ばかりでは全体が見えなくなる
- 課長は実務ができるだけではダメ
- 半分以上が実務になると「できない」を連発
- 2 課長の実務の比率を減らそう
- まず、自分がやっている仕事をすべて書き出す
- 仕事をなくすECRSを理解する
- 思い切ってECRSを実行しラクをする
- 3 部下ができる仕事は部下にまかせよう
- 課長が実務をやりすぎると部下は育たない
- 「自分がやらねば」と思うと部下にまかせられない
- 報・連・相で部下にまかせられる
- 部下にまかせても部下が帰る時間は同じ
第5章 部下の仕事を改善して減らす
- 1 部下の仕事を総点検しよう
- 部下の仕事をすべて書き出させる
- 部下の仕事を一覧表にまとめる
- 書き出した仕事を仕事の体系図と照合
- 2 不要な仕事をやめよう
- 慣習でやっている仕事をやめさせる
- 同じような仕事はまとめる
- パソコンにばかり頼らせない
- 重要でない仕事は手を抜かせる
- 仕事のやり方を個人まかせにしない
- ダラダラ仕事をさせない
- 3 忙しい人と忙しそうな人をなくそう
- 仕事の一覧表で部下の仕事量のちがいをつかむ
- 忙しい人に仕事を詰め込まない
- 忙しそうな人にはもっと仕事をしてもらう
- 4 定時帰宅を徹底しよう
- 飲み会の日は定時で終えられる
- 課長が帰らなければ部下も帰れない
- 仕事の計画を部下まかせにすれば定時には帰れない
- 手順とその内容を決めてムダな時間を排除
第6章 求められる課にする
- 1 課長の仕事は体系図で決まる
- 求められる仕事を自分でやるのが課長の役割ではない
- 課長はナビゲーター
- 仕事の交通整理をするのも役割
- 2 課長の仕事を明確にしよう
- 運営業務と職場の維持業務に分類
- 仕事の体系図から仕事を具体化
- 部下を育成するのも課長の仕事
- 課長は「どうあるべきか」が思い描けることが大切
- 3 目標を決めて求められる課にしよう
- 「どうあるべきか」と「現状」とのギャップが改善余地
- どこまでよくするかが「目標」
- 「よくするために何をするか」が課題
- 課題を具体化しなければ「絵に描いた餅」
- 目標達成管理は重要な仕事
第7章 課長の仕事はPDCA管理に集約できる
- 1 PDCA管理を理解しよう
- P(Plan:計画)は可能性が推測できるように立てる
- D(Do:実行)は目標達成に向けた行動ができるようにすること
- C(Check:確認)で問題を洗い出す
- A(Action:処置)で目標達成行動がとれるようにする
- PDCA管理サイクルを毎週回す
- 2 毎週のまとめを課長月報で分析しよう
- 成績表である課長月報で翌月の行動計画を立てる
- 「何をしたか」より「なぜできなかったか」を重視
- 管理点データで「どうすべきか」を見出す
- 「どうすべきか」の達成行動を示す
- 3 行動と結果がわかる月報をつくらせよう
- 部下の月報は「何をしたか」も記入させる
- やったことをメモらせることから始める
- 実施内容に対する問題点を明確にさせる
- 4 課の安泰は日々の管理のたまもの
- 毎日報告を受けるのが原点
- 日々のチェックが職場管理
- 「めざす方向を示す」ことが職場づくり
- コミュニケーションが職場を活性化
巻末折り込み 「課長のコミュニケーション」の基本
本書のポイント
-e1739855705335.png)
つけ麺たろう
これが分かればバッチリ…!
ポイントは「課長は、経営者と部下との橋渡しである」ということ
課長は、経営者と部下との橋渡しである、がポイントです。課長は、マネージャーと言い換えてもいいでしょう。課長とは、課の責任者です。そのため、課の役割を遂行する必要があります。
- 運営業務と維持業務
- 運営業務→目標達成、課の機能強化
- 維持業務→日々の作業、処理、決裁
課長の役割としては、半々にならないと、いけない。
ロジックツリー、目的と手段でつながる。四段階ほど。下位の機能は、部下に任せるべき。実務に寄りすぎないこと。ただ、状況による。
課の目的から、手段・機能にブレイクダウンしていく。管理点を設け、マネジメントする。例えば、営業課であれば、何かしらの数字が下ぶれていたら、改善する。
部下のリーダーの教育も必要。こちら側に来てもらう。教わると教えるの違い。(責任の違い)
究極的には、管理職は自分がいなくても組織が回る状態を作ることが大事。自分がいなくなっても回る状態を作ってからが、新しい仕事にチャレンジできるタイミング。さらに高難度・解くべき問題に取り掛かれる。

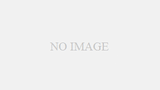
コメント